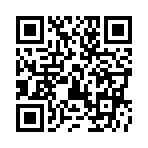アロマセラピーのこと (歴史①)
2008年11月18日
「アロマセラピー」ってなんでしょう?
アロマとは“芳香”(香りを嗅ぐこと)、
セラピーとは“治療法”という意味。
植物の中には香りを持っているものがあります。
その中の香りの成分を取り出して、私たちの身体の中に取り入れることでよい作用をもたらすこと、
それが、 「アロマセラピー」です。
「アロマセラピー」という言葉を生み出したのは、
フランスの科学者 ルネ・モーリス・ガットフォセ
1920年代になってからのことです。
実験中に片手に火傷を負い、とっさに近くにあったラベンダーの精油に手を浸けたところ、火傷は跡形も残らず驚くような早さで治ったというエピソードが残っています。
これを機に精油についての研究に取り組み、
「アロマセラピー(芳香療法)」という言葉が生まれました。
でも、 “香り”の歴史は遙か昔にさかのぼります。
古代エジプトでは紀元前3000年頃から、植物の浸出液を薬や化粧品、芳香剤として利用していたようです。
ミイラを作る際には、現在私たちがアロマセラピーで使用する“シダーウッド”や“ミルラ(没薬)”などの殺菌力の高い植物が防腐剤として使われていました。
ミイラの語源は、この「ミルラ」だと言われています。
古代ギリシャの「医学の父」ヒポクラテスは、
「健康は、芳香風呂に入り、香油マッサージを毎日行うことである。」と・・・!
芳香原料を伝染病の予防として焚くことを試みているようです。
古代ローマは、バラが生活にとても密着していた文明です。
ネロ皇帝は香り好きで、豪華なバラの花の宴会が開かれていたとか・・!
11世紀になって、植物から精油を作り出す蒸留法が開発されるとペストやコレラなどの感染症をはじめとする医療への応用も始まりました。
アロマの歴史辿るとまだまだたくさんのエピソードがあります。
数千年も前から植物に含まれる成分を、病気の予防や治療、生活そのものに利用してきたことに気づかされます。
日本でも、ゆず湯や菖蒲湯など、植物の芳香成分を利用する習慣がありますね!
アロマとは“芳香”(香りを嗅ぐこと)、
セラピーとは“治療法”という意味。
植物の中には香りを持っているものがあります。
その中の香りの成分を取り出して、私たちの身体の中に取り入れることでよい作用をもたらすこと、
それが、 「アロマセラピー」です。
「アロマセラピー」という言葉を生み出したのは、
フランスの科学者 ルネ・モーリス・ガットフォセ
1920年代になってからのことです。
実験中に片手に火傷を負い、とっさに近くにあったラベンダーの精油に手を浸けたところ、火傷は跡形も残らず驚くような早さで治ったというエピソードが残っています。
これを機に精油についての研究に取り組み、
「アロマセラピー(芳香療法)」という言葉が生まれました。
でも、 “香り”の歴史は遙か昔にさかのぼります。
古代エジプトでは紀元前3000年頃から、植物の浸出液を薬や化粧品、芳香剤として利用していたようです。
ミイラを作る際には、現在私たちがアロマセラピーで使用する“シダーウッド”や“ミルラ(没薬)”などの殺菌力の高い植物が防腐剤として使われていました。
ミイラの語源は、この「ミルラ」だと言われています。
古代ギリシャの「医学の父」ヒポクラテスは、
「健康は、芳香風呂に入り、香油マッサージを毎日行うことである。」と・・・!
芳香原料を伝染病の予防として焚くことを試みているようです。
古代ローマは、バラが生活にとても密着していた文明です。
ネロ皇帝は香り好きで、豪華なバラの花の宴会が開かれていたとか・・!
11世紀になって、植物から精油を作り出す蒸留法が開発されるとペストやコレラなどの感染症をはじめとする医療への応用も始まりました。
アロマの歴史辿るとまだまだたくさんのエピソードがあります。
数千年も前から植物に含まれる成分を、病気の予防や治療、生活そのものに利用してきたことに気づかされます。
日本でも、ゆず湯や菖蒲湯など、植物の芳香成分を利用する習慣がありますね!