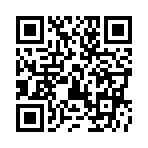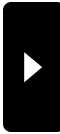スポンサーサイト
花粉が飛びますよ~~!!
2009年02月09日
いよいよ花粉の飛ぶ時期になりました
予報では、明日も・・・・!
去年まで何ともなかったのに、突然、花粉症の症状が現れることも多いようですね
花粉症におすすめのハーブティーもいろいろあります
ブログでもご紹介したエキナセアやネトル
「万能の薬箱」と呼ばれていたエルダーフラワー
民間薬として古くから親しまれてきたカモミール
強い殺菌力もあるペパーミントやスペアミント
コアラの好物のユーカリ
代表的なハーブのラベンダー
このほかにもいろんなハーブが役立ちます
お好みの味と香りのハーブティーで、
花粉症のいやーな気分と症状から抜け出しましょう
“ほろす”では、ご希望にあったハーブティーのブレンドをいたしております。
お気軽にご相談ください

予報では、明日も・・・・!
去年まで何ともなかったのに、突然、花粉症の症状が現れることも多いようですね

花粉症におすすめのハーブティーもいろいろあります

ブログでもご紹介したエキナセアやネトル
「万能の薬箱」と呼ばれていたエルダーフラワー
民間薬として古くから親しまれてきたカモミール
強い殺菌力もあるペパーミントやスペアミント
コアラの好物のユーカリ
代表的なハーブのラベンダー
このほかにもいろんなハーブが役立ちます

お好みの味と香りのハーブティーで、
花粉症のいやーな気分と症状から抜け出しましょう

“ほろす”では、ご希望にあったハーブティーのブレンドをいたしております。
お気軽にご相談ください

ネトルのハーブティー!
2009年02月08日
何か一つ“ハーブ”を買うとしたら・・・・、
おすすめは、 “ネトルリーフ” でしょうか


和名を、「セイヨウイラクサ」といい、茎にトゲのあるハーブです 。
。

懐かしい草の香りがするネトルのお茶は、
ビタミンやミネラル、鉄が豊富で、
女性にうれしい効果をもたらしてくれます 。
。
花粉症の治療薬としても注目されています。
尿酸をとりのぞいたり、血糖値を下げることも確認されているので、
糖尿病の治療薬としても研究されているようです。
いろんなハーブにブレンドすると、マイルドな味と香りが
心をホッとさせてくれます
私は、ネトルを加えてブレンドすることが多いですね
そうそう、アンデルセン童話 「白鳥の王子」のなかで、
白鳥になった兄弟の呪いを解くために、
王女がネトルから糸を紡ぐシーンがありますね!
古代では、茎からとれる繊維を利用して布を織っていたようです。
おすすめは、 “ネトルリーフ” でしょうか



和名を、「セイヨウイラクサ」といい、茎にトゲのあるハーブです
 。
。
懐かしい草の香りがするネトルのお茶は、
ビタミンやミネラル、鉄が豊富で、
女性にうれしい効果をもたらしてくれます
 。
。花粉症の治療薬としても注目されています。
尿酸をとりのぞいたり、血糖値を下げることも確認されているので、
糖尿病の治療薬としても研究されているようです。
いろんなハーブにブレンドすると、マイルドな味と香りが
心をホッとさせてくれます

私は、ネトルを加えてブレンドすることが多いですね

そうそう、アンデルセン童話 「白鳥の王子」のなかで、
白鳥になった兄弟の呪いを解くために、
王女がネトルから糸を紡ぐシーンがありますね!
古代では、茎からとれる繊維を利用して布を織っていたようです。
ラベンダーいろいろ!
2009年02月06日
まだまだ寒い冬ですが、暖かい春の庭をイメージしています
“ハーブガーデン”に植えたいハーブはたくさんありますが、
ラベンダーも敷きつめたいですね




ラベンダーといっても、種類はとっても多いんです
上の写真は、ほんの一部です!

“ハーブガーデン”に植えたいハーブはたくさんありますが、
ラベンダーも敷きつめたいですね





ラベンダーといっても、種類はとっても多いんです

上の写真は、ほんの一部です!
この時期のおすすめハーブティー!
2009年02月04日
エキナセアというハーブをご存じでしょうか?

北アメリカの先住民族が虫さされの傷の手当てに用いていた植物です。
「インディアンのハーブ」、「天然の抗生物質」ともいわれ、古くから親しまれてきました。
ここ50年ほどのあいだで、抗ウイルス、免疫強化、殺菌消毒、抗感染
作用などがあることが実証され、世界中に知られるようになりました 。
。
ガンやエイズの治療薬としても注目を浴び、
研究が進められているようです。

このエキナセアの根を使って入れるお茶は、
からだの抵抗力を高めてくれるので、
熱が出たときや、ウイルス性の風邪をひいたときには
おすすめです
勿論、病気にかかりにくい体質作りにも役立つハーブです
エキナセアはハーブティーにすると、
マイルドな草木のような風味で、
苦味や酸味などのくせがありません
お茶として楽しむなら、香りの高いハーブとブレンドするといいですね
インフルエンザにかかったときに、エキナセアのハーブティーを飲んでみてください!
発熱や喉の痛みなどの症状を和らげて、回復を助けてくれるでしょう
ビタミンCの補給もできるローズヒップとブレンドしたり、
抗炎症作用のあるエルダーフラワーとブレンドしたりすると、
美味しくて、身体にもうれしいお茶になります
ただし、多量に飲み過ぎると
めまいや吐き気を起こすことがあります!
飲み過ぎは禁物です

北アメリカの先住民族が虫さされの傷の手当てに用いていた植物です。
「インディアンのハーブ」、「天然の抗生物質」ともいわれ、古くから親しまれてきました。
ここ50年ほどのあいだで、抗ウイルス、免疫強化、殺菌消毒、抗感染
作用などがあることが実証され、世界中に知られるようになりました
 。
。ガンやエイズの治療薬としても注目を浴び、
研究が進められているようです。

このエキナセアの根を使って入れるお茶は、
からだの抵抗力を高めてくれるので、
熱が出たときや、ウイルス性の風邪をひいたときには
おすすめです

勿論、病気にかかりにくい体質作りにも役立つハーブです

エキナセアはハーブティーにすると、
マイルドな草木のような風味で、
苦味や酸味などのくせがありません

お茶として楽しむなら、香りの高いハーブとブレンドするといいですね

インフルエンザにかかったときに、エキナセアのハーブティーを飲んでみてください!
発熱や喉の痛みなどの症状を和らげて、回復を助けてくれるでしょう

ビタミンCの補給もできるローズヒップとブレンドしたり、
抗炎症作用のあるエルダーフラワーとブレンドしたりすると、
美味しくて、身体にもうれしいお茶になります

ただし、多量に飲み過ぎると
めまいや吐き気を起こすことがあります!
飲み過ぎは禁物です

インフルエンザが流行~!!
2009年02月04日
久しぶりのブログ更新です
周囲に心不全や脳梗塞などで入院する人が相次ぎ、あらためて健康の有り難さと大切さを痛感しているところです
定期的な健康診断は必要ですね
ところで、インフルエンザ 流行していますね~!!
インフルエンザの予防には、
予防接種は勿論ですが、
うがいや手洗い、加湿などがあげられます
外出先から帰ったら、うがいをじゅうぶんにし、
手洗いも20秒以上必要だそうです。
インフルエンザウイルスは湿気に弱いので、
50~60%の湿度が望ましいと言われます。
加湿器を利用するのもいいですね。
インフルエンザの予防
でご紹介した精油をアロマ対応の加湿器に入れると、
湿度に加えて精油の抗菌作用と香りがお部屋に漂って、
予防効果大です
ご家庭でできることをやってみられませんか

周囲に心不全や脳梗塞などで入院する人が相次ぎ、あらためて健康の有り難さと大切さを痛感しているところです

定期的な健康診断は必要ですね

ところで、インフルエンザ 流行していますね~!!
インフルエンザの予防には、
予防接種は勿論ですが、
うがいや手洗い、加湿などがあげられます

外出先から帰ったら、うがいをじゅうぶんにし、
手洗いも20秒以上必要だそうです。
インフルエンザウイルスは湿気に弱いので、
50~60%の湿度が望ましいと言われます。
加湿器を利用するのもいいですね。
インフルエンザの予防
でご紹介した精油をアロマ対応の加湿器に入れると、
湿度に加えて精油の抗菌作用と香りがお部屋に漂って、
予防効果大です

ご家庭でできることをやってみられませんか

サフラワー(ベニバナ)のこと!
2009年01月07日
ハーブティーのオーダーに、最近よくブレンドするのが
“サフラワー”


「ベニバナ」といった方が親しみがあるかも知れませんね。
昔から染料としても使われてきました。
私自身も、更年期の症状で、突然汗が噴き出したり、めまいがしたりと悩まされたころ助けられたハーブです
サフラワーには、血行を促してからだを温めたり、
ホルモンバランスを整える作用があります。
生理不順や冷え性、肌荒れ、更年期障害など、女性にうれしいハーブ
ハーブティーのブレンドを希望されるお客様は、女性が多く、年齢的にもサフラワーが功を奏すことが多いようです。
産後にもオススメで、母乳の出を良くする作用もあるんです
カモミールやリンデンなどとブレンドすると、
疲れもとりイライラした気分もしずめてリラックスできそうです
ただし、子宮を収縮する作用があるので
妊娠中は使用を避けます
ハーブティーの色と香りを楽しんでみませんか。
心と身体も喜んでくれるはずですよ
“サフラワー”


「ベニバナ」といった方が親しみがあるかも知れませんね。
昔から染料としても使われてきました。
私自身も、更年期の症状で、突然汗が噴き出したり、めまいがしたりと悩まされたころ助けられたハーブです

サフラワーには、血行を促してからだを温めたり、
ホルモンバランスを整える作用があります。
生理不順や冷え性、肌荒れ、更年期障害など、女性にうれしいハーブ
ハーブティーのブレンドを希望されるお客様は、女性が多く、年齢的にもサフラワーが功を奏すことが多いようです。
産後にもオススメで、母乳の出を良くする作用もあるんです

カモミールやリンデンなどとブレンドすると、
疲れもとりイライラした気分もしずめてリラックスできそうです

ただし、子宮を収縮する作用があるので
妊娠中は使用を避けます

ハーブティーの色と香りを楽しんでみませんか。
心と身体も喜んでくれるはずですよ

うれし~い一言!!
2008年12月14日
注文のブレンドハーブティーを取りに来られたお客様
3人の子供さんのお母様です
肌荒れがとても気になられていて、ハーブティーを試したいと
相談に見えたのは10月半ばのこと。
お仕事もされていて疲れも溜まっていらっしゃるようだし、
ストレスやホルモンバランスも・・・
ホルモンバランスを整えるハーブや、ビタミンやミネラルの豊富なハーブなど女性にうれしいハーブ数種類をブレンドしました
今回が3度目の注文ですが、
「このハーブティーを飲み始めてから、
疲れがとれて肌の状態も
とても良くなってきたんですよ~ 」
」
とてもうれしい一言です

以前は、1日1本はドリンク剤を飲んでいたそうです
身体ともに活力が満ち、バランスのとれた状態になっていくのを
ハーブが手助けしてくれたんですね
心身に染みわたって、私たちが本来持っている力を引き出してくれる
ハーブ


ハーブの力をたくさんの方に実感してほしいですね

3人の子供さんのお母様です

肌荒れがとても気になられていて、ハーブティーを試したいと
相談に見えたのは10月半ばのこと。
お仕事もされていて疲れも溜まっていらっしゃるようだし、
ストレスやホルモンバランスも・・・

ホルモンバランスを整えるハーブや、ビタミンやミネラルの豊富なハーブなど女性にうれしいハーブ数種類をブレンドしました

今回が3度目の注文ですが、
「このハーブティーを飲み始めてから、
疲れがとれて肌の状態も
とても良くなってきたんですよ~
 」
」とてもうれしい一言です


以前は、1日1本はドリンク剤を飲んでいたそうです

身体ともに活力が満ち、バランスのとれた状態になっていくのを
ハーブが手助けしてくれたんですね

心身に染みわたって、私たちが本来持っている力を引き出してくれる
ハーブ



ハーブの力をたくさんの方に実感してほしいですね

ラベンダー精油のすごさ!
2008年12月07日
“アロマ”と言うと、
“ラベンダー”を一番に思い浮かべる方が多いようです。
ラベンダーは、常備する精油としてお勧めするものの一つですね
そこで、今日は“ラベンダー”のエッセンシャルオイルについて書いてみようと思います
ラベンダーのエッセンシャルオイルにはいろんな種類があるので、
一番入手しやすく一般的な「angustifolia」を例にします。
ラベンダーのエッセンシャルオイルの主成分は、
酢酸リナリルとリナロール。
酢酸リナリルは、心身のアンバランスを正常な状態に戻す作用や、
抗痙攣作用を示す代表的な成分です。
ラベンダーにリラックス作用があると言われるのは、
この成分を40%も含んでいるため
また、これが皮膚を痛めるような毒性を持たない成分なため、
安全性が高く初心者向けと言われています。
リナロールという成分には、
殺菌作用、抗ウイルス作用、抗真菌作用などがあります。
洗濯機の中にラベンダーを1~2滴垂らすと、
香りが楽しめると同時に除菌効果も期待できます
掃除機の集塵パックに1~2滴垂らすと、
ホコリなどの嫌な臭いが取り除かれます
アイロンをかける時にスチームスプレーの中へ1~2滴垂らすと、
衣類を清潔に保ってくれます
リナロールも酢酸リナリルも皮膚への毒性はありません
これらの成分を多く含むラベンダーの精油は気軽に安心して用いることができる精油です。
そして、心や身体に働きかける
「万能なエッセンシャルオイル」
と言われる所以なんです
ただし、「angustifolia」以外のラベンダーの精油も種類が多くあるので、成分を確かめてお使いになることをお勧めします。
“ラベンダーの精油”と言って購入してもリラックス作用のないものもあるわけですから・・・・!
“ラベンダー”を一番に思い浮かべる方が多いようです。
ラベンダーは、常備する精油としてお勧めするものの一つですね

そこで、今日は“ラベンダー”のエッセンシャルオイルについて書いてみようと思います

ラベンダーのエッセンシャルオイルにはいろんな種類があるので、
一番入手しやすく一般的な「angustifolia」を例にします。
ラベンダーのエッセンシャルオイルの主成分は、
酢酸リナリルとリナロール。
酢酸リナリルは、心身のアンバランスを正常な状態に戻す作用や、
抗痙攣作用を示す代表的な成分です。
ラベンダーにリラックス作用があると言われるのは、
この成分を40%も含んでいるため

また、これが皮膚を痛めるような毒性を持たない成分なため、
安全性が高く初心者向けと言われています。
リナロールという成分には、
殺菌作用、抗ウイルス作用、抗真菌作用などがあります。
洗濯機の中にラベンダーを1~2滴垂らすと、
香りが楽しめると同時に除菌効果も期待できます

掃除機の集塵パックに1~2滴垂らすと、
ホコリなどの嫌な臭いが取り除かれます

アイロンをかける時にスチームスプレーの中へ1~2滴垂らすと、
衣類を清潔に保ってくれます

リナロールも酢酸リナリルも皮膚への毒性はありません

これらの成分を多く含むラベンダーの精油は気軽に安心して用いることができる精油です。
そして、心や身体に働きかける
「万能なエッセンシャルオイル」
と言われる所以なんです

ただし、「angustifolia」以外のラベンダーの精油も種類が多くあるので、成分を確かめてお使いになることをお勧めします。
“ラベンダーの精油”と言って購入してもリラックス作用のないものもあるわけですから・・・・!
インフルエンザの予防~!!
2008年12月01日
今年も、インフルエンザが流行する季節になりました
私も3年ほど前に、しかも大晦日の午後から高熱を出して、
最悪の新年を過ごしたことがあります。
インフルエンザに罹ってみないと解らない
‘節々の痛み!何とも言えない身体のだるさ!’
もう二度と、インフルエンザには罹りたくないですね
そこで、インフルエンザの予防にお勧めの
“芳香浴” をご紹介します


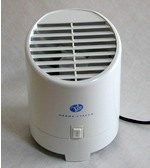



インテリアとしても楽しめるいろんな芳香器もあります
ティートゥリー 2滴
ユーカリ 2滴
レモン 2滴
を芳香器に入れて、お部屋に香りを拡散させて下さい
芳香器がなければ、
マグカップや洗面器に40~50度くらいのお湯を注ぎ、
その中に精油を加えてもOKですよ
殺菌・抗ウイルス作用の強い成分を含む精油が
お部屋の空気を浄化してくれますよ
お店の中や、事務所にもインフルエンザ予防のために、
香りを漂わせてはいかがでしょうか
もちろん、栄養と休養を十分にとって
体調管理をすることもお忘れなく

私も3年ほど前に、しかも大晦日の午後から高熱を出して、
最悪の新年を過ごしたことがあります。
インフルエンザに罹ってみないと解らない
‘節々の痛み!何とも言えない身体のだるさ!’
もう二度と、インフルエンザには罹りたくないですね

そこで、インフルエンザの予防にお勧めの
“芳香浴” をご紹介します



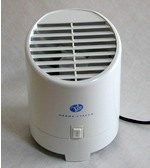



インテリアとしても楽しめるいろんな芳香器もあります

ティートゥリー 2滴
ユーカリ 2滴
レモン 2滴
を芳香器に入れて、お部屋に香りを拡散させて下さい

芳香器がなければ、
マグカップや洗面器に40~50度くらいのお湯を注ぎ、
その中に精油を加えてもOKですよ

殺菌・抗ウイルス作用の強い成分を含む精油が
お部屋の空気を浄化してくれますよ

お店の中や、事務所にもインフルエンザ予防のために、
香りを漂わせてはいかがでしょうか

もちろん、栄養と休養を十分にとって
体調管理をすることもお忘れなく

アロマセラピーのこと (足の冷えに~!)
2008年11月23日
“ほろす”で、最近多いのが
「冷え性に良いハーブティー」のご注文
血行をよくして身体を温めるハーブをブレンドしています。
そこで、これからの時期にもう一つおすすめなのが、
“足浴”です
簡単にできる“足浴”をご紹介します
用意するものは、
バケツか洗面器 (くるぶしまでつかるもの)
精油 (3滴)
・バケツか洗面器に40度きらいのお湯を入れます。
・精油3滴を入れて、よくかき混ぜ、
足をつけて10分ほどリラ~ックスします。
夜、休む前にゆったりした気持ちでやってみてください。
疲れもとれて、暖かく眠れますよ
おすすめの精油は、
・緊張をほぐし、眠りを誘ってくれるラベンダー
・抗真菌作用や抗ウイルス作用が期待されるティートゥリー
(水虫に悩んでいる方や風邪をひきそうな方!)
・足の疲れやむくみにおすすめのジュニパーやレモン
などなど・・・・
「足が冷たくて靴下をはいて寝ないと眠れない」という方
是非おためし下さい
実は私、足が温まらず、初めて靴下をはいて寝ました
早速、“足浴”を実践・・・・・Good でしたよ
でしたよ
“ほろす”では、アロマ手作り教室など、
身近で生かせるアロマについてのアドバイスもいたしております
「冷え性に良いハーブティー」のご注文

血行をよくして身体を温めるハーブをブレンドしています。
そこで、これからの時期にもう一つおすすめなのが、
“足浴”です

簡単にできる“足浴”をご紹介します

用意するものは、
バケツか洗面器 (くるぶしまでつかるもの)
精油 (3滴)
・バケツか洗面器に40度きらいのお湯を入れます。
・精油3滴を入れて、よくかき混ぜ、
足をつけて10分ほどリラ~ックスします。
夜、休む前にゆったりした気持ちでやってみてください。
疲れもとれて、暖かく眠れますよ

おすすめの精油は、
・緊張をほぐし、眠りを誘ってくれるラベンダー
・抗真菌作用や抗ウイルス作用が期待されるティートゥリー
(水虫に悩んでいる方や風邪をひきそうな方!)
・足の疲れやむくみにおすすめのジュニパーやレモン
などなど・・・・
「足が冷たくて靴下をはいて寝ないと眠れない」という方

是非おためし下さい

実は私、足が温まらず、初めて靴下をはいて寝ました

早速、“足浴”を実践・・・・・Good
 でしたよ
でしたよ
“ほろす”では、アロマ手作り教室など、
身近で生かせるアロマについてのアドバイスもいたしております

朝の畑! (Before~ “ハーブガーデン”)
2008年11月23日

朝、孫の声で目を覚ますと、
なに~~っ!!7時20分~~~???
実は、昨夜は孫を寝かしつけながら、そのまま
爆睡してしまっていたんです


ブログも書かず、見たかったテレビもみないまま・・・・

でも、そこは立ち直りの早いのが取り柄の‘ほろす’です

“ほろすのハーブガーデン”を夢見ながら、早速現場へ

庭の向こうに見える荒れた畑・・・




今でも、とりあえずの“ハーブ”や“実のなる木”たちが
散在してはいるんですが・・・・・





さ~て、どんな“ハーブガーデン”になることでしょうか?
来春に向けて、ぼちぼちと頑張りま~す

畑の成長の様子とハーブのことも、
ぼちぼちとブログにアップしたいと思います

アロマセラピーのこと (香りのルート)
2008年11月22日
精油の“香り”を楽しむとき、身体の中ではどんな変化が起こるのでしょう?
香りは空気中で小さな分子として飛び回っています。
その分子が体内に入るのには、主に3つのルートがあります。



☆鼻から脳へ
香りの小さな分子は鼻の中を転がって、
鼻の奥にある嗅細胞から大脳辺縁系へ届きます。
免疫系やホルモンの分泌をコントロールする視床下部や、
記憶や感情、情動をたずさわる場所に伝わって、
いろんな変化をもたらします。
リラックスしたり、しゃきっとしたりと、影響はさまざま
たとえば、ラベンダーの香りは気持ちを和らげ眠りを誘います。
ローズマリーは集中力や記憶力を高め、気分をリフレッシュ
する働きがあります。
☆鼻から肺へ
香りの分子は呼吸と一緒に鼻や口から喉を通って気管や気管支、
肺へと入っていきます。
そして、肺の粘膜から吸収されて血液に流れ込みます。
精油を吸い込むと、約5分後には血液中に精油の
芳香成分が出てくるそうですよ
インフルエンザが流行る時期に部屋に
精油を香らせるだけでも作用が期待されます。
眠るために部屋にラベンダーを香らせると、
同時に吸入もできるわけですね
☆皮膚から血液中へ
精油を入れたお湯につかったり、塗布やマッサージを
することで、香りの成分が皮膚からも浸透します
皮膚の表皮にはバリアゾーンがあって、
ほとんどの物質は通過できません。
しかし、芳香成分の分子はとても小さいのでバリアを
通りぬけて、毛細血管から全身へと運ばれるんです。
精油をスキンケアに使うことで、精油のいろいろな作用が
肌だけでなく、身体全体に働きかけてくれます
香りは 「あ~、良い香り!」というだけでなく、
身体や心にいろんな働きかけをしてくれます
自然からの贈り物、「精油の香り」をもっと知り、生活の中で楽しみながら
心も身体も健やかでありたいものです
でも、一番大切なのは
“自分が好きな香り”であること
ですね
香りは空気中で小さな分子として飛び回っています。
その分子が体内に入るのには、主に3つのルートがあります。



☆鼻から脳へ
香りの小さな分子は鼻の中を転がって、
鼻の奥にある嗅細胞から大脳辺縁系へ届きます。
免疫系やホルモンの分泌をコントロールする視床下部や、
記憶や感情、情動をたずさわる場所に伝わって、
いろんな変化をもたらします。
リラックスしたり、しゃきっとしたりと、影響はさまざま

たとえば、ラベンダーの香りは気持ちを和らげ眠りを誘います。
ローズマリーは集中力や記憶力を高め、気分をリフレッシュ
する働きがあります。
☆鼻から肺へ
香りの分子は呼吸と一緒に鼻や口から喉を通って気管や気管支、
肺へと入っていきます。
そして、肺の粘膜から吸収されて血液に流れ込みます。
精油を吸い込むと、約5分後には血液中に精油の
芳香成分が出てくるそうですよ

インフルエンザが流行る時期に部屋に
精油を香らせるだけでも作用が期待されます。
眠るために部屋にラベンダーを香らせると、
同時に吸入もできるわけですね

☆皮膚から血液中へ
精油を入れたお湯につかったり、塗布やマッサージを
することで、香りの成分が皮膚からも浸透します

皮膚の表皮にはバリアゾーンがあって、
ほとんどの物質は通過できません。
しかし、芳香成分の分子はとても小さいのでバリアを
通りぬけて、毛細血管から全身へと運ばれるんです。
精油をスキンケアに使うことで、精油のいろいろな作用が
肌だけでなく、身体全体に働きかけてくれます

香りは 「あ~、良い香り!」というだけでなく、
身体や心にいろんな働きかけをしてくれます

自然からの贈り物、「精油の香り」をもっと知り、生活の中で楽しみながら
心も身体も健やかでありたいものです

でも、一番大切なのは
“自分が好きな香り”であること
ですね

アロマセラピーのこと (ゆず)
2008年11月21日
庭に鈴なりの“ゆず”は、ほぼ毎日料理に利用されている我が家です。
あの風味が何とも言えません

“ゆず”の精油はなかなか手に入りにくいようですが・・・・
‘生活の木’には製品がありますね。“ほろす”にも・・!
“ゆず”はお料理やお風呂などによく用いられます。
心も体も温めて元気にしてくれる香りです
主な成分は、柑橘系に多いリモネンですが、微量に含まれるチモールやペリラアルデヒドなどが“ゆず特有の香り”を作り出しています。
冬至には、 「ゆず湯」に入りますね
「成分中の“リモネン”が血行を促し、体を温め、風邪をひきにくくする」
そして、
「健康に融通がききますように」
という願いも込めて使用していたんだとか・・・
“ゆずの精油”をお風呂にそのまま入れると、
皮膚に刺激になることがあります。
オレンジなどの精油でも、皮膚刺激を感じることがありますよ!
(個人差があるようですが、
私は、オレンジの精油で体がジカジカします )
)
また、柑橘系の精油は、皮膚につけたまま日光に当たると、
皮膚に色素沈着や炎症を起こすことがあります。
これを、 「光毒性(日光感作性)」といいますが、
肌につけてから4~5時間は日光に当たらないようにしてください
精油は自然からの贈り物です。
正しい使い方をして楽しみたいものですね
あの風味が何とも言えません


“ゆず”の精油はなかなか手に入りにくいようですが・・・・

‘生活の木’には製品がありますね。“ほろす”にも・・!
“ゆず”はお料理やお風呂などによく用いられます。
心も体も温めて元気にしてくれる香りです

主な成分は、柑橘系に多いリモネンですが、微量に含まれるチモールやペリラアルデヒドなどが“ゆず特有の香り”を作り出しています。
冬至には、 「ゆず湯」に入りますね

「成分中の“リモネン”が血行を促し、体を温め、風邪をひきにくくする」
そして、
「健康に融通がききますように」
という願いも込めて使用していたんだとか・・・

“ゆずの精油”をお風呂にそのまま入れると、
皮膚に刺激になることがあります。
オレンジなどの精油でも、皮膚刺激を感じることがありますよ!
(個人差があるようですが、
私は、オレンジの精油で体がジカジカします
 )
)また、柑橘系の精油は、皮膚につけたまま日光に当たると、
皮膚に色素沈着や炎症を起こすことがあります。
これを、 「光毒性(日光感作性)」といいますが、
肌につけてから4~5時間は日光に当たらないようにしてください

精油は自然からの贈り物です。
正しい使い方をして楽しみたいものですね

アロマセラピーのこと (精油の抽出法)
2008年11月20日
植物から精油(エッセンシャルオイル)を採る方法は?
主な抽出方法には圧搾法と水蒸気蒸留法の二つがあります。
・圧搾法・・・果皮を押しつぶしてエッセンスを搾り出します。
レモンやオレンジなどの柑橘類は、果皮の外側に
芳香成分が多く含まれているので、この方法が適します。

・水蒸気蒸留法・・・低温で時間をかけて抽出する最も一般的な方法。
原料を蒸し、そこから出る香りの蒸気を冷やして
水分と精油成分とに分離します。

では、植物から採れる精油の量は、どのくらいなんでしょう??
植物に含まれる芳香物質の量は、0.01~10%とごくわずか
この量によって精油の量も決まります。
1kgの精油を作るために必要な花は、
ラベンダーなら・・・・100kg
バラなら・・・・・・・・・・2000kg
ローズの精油1滴には、
なんと約50本ものバラの花びらが使われているんです
ローズの精油が高価なわけですね
主な抽出方法には圧搾法と水蒸気蒸留法の二つがあります。
・圧搾法・・・果皮を押しつぶしてエッセンスを搾り出します。
レモンやオレンジなどの柑橘類は、果皮の外側に
芳香成分が多く含まれているので、この方法が適します。

・水蒸気蒸留法・・・低温で時間をかけて抽出する最も一般的な方法。
原料を蒸し、そこから出る香りの蒸気を冷やして
水分と精油成分とに分離します。

では、植物から採れる精油の量は、どのくらいなんでしょう??
植物に含まれる芳香物質の量は、0.01~10%とごくわずか

この量によって精油の量も決まります。
1kgの精油を作るために必要な花は、
ラベンダーなら・・・・100kg
バラなら・・・・・・・・・・2000kg
ローズの精油1滴には、
なんと約50本ものバラの花びらが使われているんです

ローズの精油が高価なわけですね

アロマセラピーのこと (精油)
2008年11月18日
アロマの歴史を辿っていくと、人と香りとの関係が深くて古いことに気づきます
現代のように生活が複雑でなく、シンプルだった頃は、“香り”はもっと生活に密着していたんでしょうね。
植物から抽出された「精油」を利用して心身を癒し元気づける「アロマセラピー」
アロマセラピーに欠かせない「精油」って何でしょう?
「精油」は「エッセンシャルオイル」といいますが、オイルという名に反して、油の成分の脂質類はほとんど含まれません。
でも、水には溶けず、油にはよく溶ける性質を持っているんです。
強いて言えばアルコールに近いもので、揮発性があり、ベタつく感触はありません。
「精油」の原料となるのは、植物の花や葉、種子や根、樹脂などいろいろです。
ハーブや柑橘類などの植物には、「油のう」と呼ばれる袋状の小さい粒があって、この粒の中に精油が入っています。
オレンジなどの皮の表面をよく見ると、透明感のある油のうが確認できますよ。
この「油のう」が花びら、樹皮、果皮、茎、葉の裏など、植物のいろんな部位にあって、そこから精油が採られます。
オレンジの皮をギュッと押さえると、“プチッ”と香りの強い液が出てきますよね
これがオレンジの精油です!
「植物のホルモン」とも呼ばれる精油。
根から水分や栄養を吸収し、たくさんの日光を浴びて育った植物は、自然が与えてくれた力を、自分が育つための力に変換させ、「油のう」にため込んでいるんです。
「精油」には、植物が大地や太陽から受け取ったパワーが凝縮されているんですね
どんな植物のどの部位から抽出されたかによって、
成分も私たちにもたらす影響も変わってきます。
「精油」の抽出法は、次回へ~!

現代のように生活が複雑でなく、シンプルだった頃は、“香り”はもっと生活に密着していたんでしょうね。
植物から抽出された「精油」を利用して心身を癒し元気づける「アロマセラピー」

アロマセラピーに欠かせない「精油」って何でしょう?
「精油」は「エッセンシャルオイル」といいますが、オイルという名に反して、油の成分の脂質類はほとんど含まれません。
でも、水には溶けず、油にはよく溶ける性質を持っているんです。
強いて言えばアルコールに近いもので、揮発性があり、ベタつく感触はありません。
「精油」の原料となるのは、植物の花や葉、種子や根、樹脂などいろいろです。
ハーブや柑橘類などの植物には、「油のう」と呼ばれる袋状の小さい粒があって、この粒の中に精油が入っています。
オレンジなどの皮の表面をよく見ると、透明感のある油のうが確認できますよ。
この「油のう」が花びら、樹皮、果皮、茎、葉の裏など、植物のいろんな部位にあって、そこから精油が採られます。
オレンジの皮をギュッと押さえると、“プチッ”と香りの強い液が出てきますよね

これがオレンジの精油です!
「植物のホルモン」とも呼ばれる精油。
根から水分や栄養を吸収し、たくさんの日光を浴びて育った植物は、自然が与えてくれた力を、自分が育つための力に変換させ、「油のう」にため込んでいるんです。
「精油」には、植物が大地や太陽から受け取ったパワーが凝縮されているんですね

どんな植物のどの部位から抽出されたかによって、
成分も私たちにもたらす影響も変わってきます。
「精油」の抽出法は、次回へ~!
アロマセラピーのこと (歴史①)
2008年11月18日
「アロマセラピー」ってなんでしょう?
アロマとは“芳香”(香りを嗅ぐこと)、
セラピーとは“治療法”という意味。
植物の中には香りを持っているものがあります。
その中の香りの成分を取り出して、私たちの身体の中に取り入れることでよい作用をもたらすこと、
それが、 「アロマセラピー」です。
「アロマセラピー」という言葉を生み出したのは、
フランスの科学者 ルネ・モーリス・ガットフォセ
1920年代になってからのことです。
実験中に片手に火傷を負い、とっさに近くにあったラベンダーの精油に手を浸けたところ、火傷は跡形も残らず驚くような早さで治ったというエピソードが残っています。
これを機に精油についての研究に取り組み、
「アロマセラピー(芳香療法)」という言葉が生まれました。
でも、 “香り”の歴史は遙か昔にさかのぼります。
古代エジプトでは紀元前3000年頃から、植物の浸出液を薬や化粧品、芳香剤として利用していたようです。
ミイラを作る際には、現在私たちがアロマセラピーで使用する“シダーウッド”や“ミルラ(没薬)”などの殺菌力の高い植物が防腐剤として使われていました。
ミイラの語源は、この「ミルラ」だと言われています。
古代ギリシャの「医学の父」ヒポクラテスは、
「健康は、芳香風呂に入り、香油マッサージを毎日行うことである。」と・・・!
芳香原料を伝染病の予防として焚くことを試みているようです。
古代ローマは、バラが生活にとても密着していた文明です。
ネロ皇帝は香り好きで、豪華なバラの花の宴会が開かれていたとか・・!
11世紀になって、植物から精油を作り出す蒸留法が開発されるとペストやコレラなどの感染症をはじめとする医療への応用も始まりました。
アロマの歴史辿るとまだまだたくさんのエピソードがあります。
数千年も前から植物に含まれる成分を、病気の予防や治療、生活そのものに利用してきたことに気づかされます。
日本でも、ゆず湯や菖蒲湯など、植物の芳香成分を利用する習慣がありますね!
アロマとは“芳香”(香りを嗅ぐこと)、
セラピーとは“治療法”という意味。
植物の中には香りを持っているものがあります。
その中の香りの成分を取り出して、私たちの身体の中に取り入れることでよい作用をもたらすこと、
それが、 「アロマセラピー」です。
「アロマセラピー」という言葉を生み出したのは、
フランスの科学者 ルネ・モーリス・ガットフォセ
1920年代になってからのことです。
実験中に片手に火傷を負い、とっさに近くにあったラベンダーの精油に手を浸けたところ、火傷は跡形も残らず驚くような早さで治ったというエピソードが残っています。
これを機に精油についての研究に取り組み、
「アロマセラピー(芳香療法)」という言葉が生まれました。
でも、 “香り”の歴史は遙か昔にさかのぼります。
古代エジプトでは紀元前3000年頃から、植物の浸出液を薬や化粧品、芳香剤として利用していたようです。
ミイラを作る際には、現在私たちがアロマセラピーで使用する“シダーウッド”や“ミルラ(没薬)”などの殺菌力の高い植物が防腐剤として使われていました。
ミイラの語源は、この「ミルラ」だと言われています。
古代ギリシャの「医学の父」ヒポクラテスは、
「健康は、芳香風呂に入り、香油マッサージを毎日行うことである。」と・・・!
芳香原料を伝染病の予防として焚くことを試みているようです。
古代ローマは、バラが生活にとても密着していた文明です。
ネロ皇帝は香り好きで、豪華なバラの花の宴会が開かれていたとか・・!
11世紀になって、植物から精油を作り出す蒸留法が開発されるとペストやコレラなどの感染症をはじめとする医療への応用も始まりました。
アロマの歴史辿るとまだまだたくさんのエピソードがあります。
数千年も前から植物に含まれる成分を、病気の予防や治療、生活そのものに利用してきたことに気づかされます。
日本でも、ゆず湯や菖蒲湯など、植物の芳香成分を利用する習慣がありますね!
アロマセラピーのこと (アロマとの出会い)
2008年11月17日
“アロマセラピー”というと、皆さんはどんなイメージを持ちますか?
香り?癒し?リラックス?・・・・
数年前までの私のイメージは、いい香りを嗅いで心地よく・・・・という程度のものでした。

病院薬剤師としてフルに働いていた私には、病気を治すためには、まず‘薬’という意識があり、アロマセラピーやいろいろな代替医療についても何となく受け入れられずにいたんです。
でも、「予防医学」という考え方が広まり、勤務先の病院でも「患者様中心の医療」という意識が高まっていく中で、
・患者様が求めているもの
・患者様のためにできること
・患者様のためにしなくてはならないこと
が何なのかと悩み考えるようになりました。
たまたま、主人が知人からもらってきたハーブの苗を庭に植えて育てるうちに、ハーブに興味が出てきて・・・。
いろいろなハーブを植えてみたり、本を読んでみたりしながら、ハーブを身近に感じるようになっていきました。
でも、まだこの頃は趣味の範囲でしたね。
今思うとこの頃から、病気・予防・人間・医療・・・に今までとは違った思いを持ち始めていたような・・・・
そんな中、次男の結婚・同居・孫の誕生・・・と生活環境が大きく変わり・・・・・
「この辺で、ちょっと頑張り方を変えようかな 」と一大決心
」と一大決心
25年半の仕事中心の生活にピリオドを打ちました。
病気の原因にもなっている環境問題や、添加物、サプリメントなどにも興味があったので、医療現場から離れて毎日の生活を見直すことに
仕事を辞めて感じたのは、
「こんな生活もあったんだな~~ 」
」
しかし、それまでの25年半がどれだけ私自身を育ててくれていたのか、後になって気づかされるんです。
では、アロマとの出会いは??・・・というと、
ある日、立ち寄った本屋さんで何気なく手に取ったのが、
「アロマセラピーの資格を取るための本」
そのときは、アロマの資格を取りたいとは思っていなかったんですが・・・。
何と家に帰ってから、本に書いてあった東京の協会に電話した私・・・!!
とても考えられないことです
すると、アロマのスクールが熊本にもあることを教えてくださって・・・・!!
またまた、そのスクールに電話を・・・!!!
「今度の土曜日に、アロマの講座の説明会がありますよ 」とのこと。
」とのこと。
二つ返事で、「参加します 」
」
言うまでもなく、アロマの講座の説明会の後、受講申込みを済ませてきていました
こんな流れで、アロマセラピーを勉強することになったわけです
アロマセラピーについて、少しずつ書いていきますね
香り?癒し?リラックス?・・・・
数年前までの私のイメージは、いい香りを嗅いで心地よく・・・・という程度のものでした。

病院薬剤師としてフルに働いていた私には、病気を治すためには、まず‘薬’という意識があり、アロマセラピーやいろいろな代替医療についても何となく受け入れられずにいたんです。
でも、「予防医学」という考え方が広まり、勤務先の病院でも「患者様中心の医療」という意識が高まっていく中で、
・患者様が求めているもの
・患者様のためにできること
・患者様のためにしなくてはならないこと
が何なのかと悩み考えるようになりました。
たまたま、主人が知人からもらってきたハーブの苗を庭に植えて育てるうちに、ハーブに興味が出てきて・・・。
いろいろなハーブを植えてみたり、本を読んでみたりしながら、ハーブを身近に感じるようになっていきました。
でも、まだこの頃は趣味の範囲でしたね。
今思うとこの頃から、病気・予防・人間・医療・・・に今までとは違った思いを持ち始めていたような・・・・

そんな中、次男の結婚・同居・孫の誕生・・・と生活環境が大きく変わり・・・・・

「この辺で、ちょっと頑張り方を変えようかな
 」と一大決心
」と一大決心
25年半の仕事中心の生活にピリオドを打ちました。
病気の原因にもなっている環境問題や、添加物、サプリメントなどにも興味があったので、医療現場から離れて毎日の生活を見直すことに

仕事を辞めて感じたのは、
「こんな生活もあったんだな~~
 」
」しかし、それまでの25年半がどれだけ私自身を育ててくれていたのか、後になって気づかされるんです。
では、アロマとの出会いは??・・・というと、
ある日、立ち寄った本屋さんで何気なく手に取ったのが、
「アロマセラピーの資格を取るための本」

そのときは、アロマの資格を取りたいとは思っていなかったんですが・・・。
何と家に帰ってから、本に書いてあった東京の協会に電話した私・・・!!
とても考えられないことです

すると、アロマのスクールが熊本にもあることを教えてくださって・・・・!!
またまた、そのスクールに電話を・・・!!!
「今度の土曜日に、アロマの講座の説明会がありますよ
 」とのこと。
」とのこと。二つ返事で、「参加します
 」
」言うまでもなく、アロマの講座の説明会の後、受講申込みを済ませてきていました

こんな流れで、アロマセラピーを勉強することになったわけです

アロマセラピーについて、少しずつ書いていきますね

なんて元気なの~~!
2008年11月12日
このところ急に寒くなった矢部!
間近に迫った冬の気配を感じます
野菜の収穫も終わって、すっかり淋しくなった畑に出てみました。



[フェンネル] [チェリーセージ] [メドウセージ]



[ボリジ] [ヤロー] [ナスタチウム]
先月、夏の間元気に生い茂っていたハーブたちは、剪定されたり刈り取られたりして、姿が見えなくなっていたのですが・・・・
なんと、みんなみんな、こんなに生き生き元気にしているではありませんか


なんとけなげで、なんと逞しくて素敵なんでしょう
自然のエネルギーってスゴイですね!
自然の恵みに感謝、脱帽~~
そのパワーをたくさんいただきま~す
ところで、このハーブたち、冬はどうしてあげたらいいんでしょうか??
どなたかアドバイスをお願いしま~す
間近に迫った冬の気配を感じます

野菜の収穫も終わって、すっかり淋しくなった畑に出てみました。



[フェンネル] [チェリーセージ] [メドウセージ]



[ボリジ] [ヤロー] [ナスタチウム]
先月、夏の間元気に生い茂っていたハーブたちは、剪定されたり刈り取られたりして、姿が見えなくなっていたのですが・・・・

なんと、みんなみんな、こんなに生き生き元気にしているではありませんか



なんとけなげで、なんと逞しくて素敵なんでしょう

自然のエネルギーってスゴイですね!
自然の恵みに感謝、脱帽~~

そのパワーをたくさんいただきま~す

ところで、このハーブたち、冬はどうしてあげたらいいんでしょうか??
どなたかアドバイスをお願いしま~す

ただいま、準備中~、焦ってますぅ~~!!
2008年10月24日
「山都町有機農産物フェアー2008」に出品するハーブティーをブレンドしています。

お天気が良ければいいですが・・・。
いちごいちえの「苺氷り」も販売いたしま~す
「苺氷り」の今年の販売は、今回で終了。
また来年~~!
「天草灘の海の塩」や山都産の有機米を使った「有機純米酢」、「赤ぶどう酢」・・・・。
「お風呂のハーブ」に「ブレンドハーブティー」・・・・。
アロマスプレー手作り体験・・・。
明日は会場設営の準備です。
とにかく焦りながら準備中です
たくさんの方々に楽しんでいただけるよう頑張りま~す

お天気が良ければいいですが・・・。
いちごいちえの「苺氷り」も販売いたしま~す

「苺氷り」の今年の販売は、今回で終了。
また来年~~!
「天草灘の海の塩」や山都産の有機米を使った「有機純米酢」、「赤ぶどう酢」・・・・。
「お風呂のハーブ」に「ブレンドハーブティー」・・・・。
アロマスプレー手作り体験・・・。
明日は会場設営の準備です。
とにかく焦りながら準備中です

たくさんの方々に楽しんでいただけるよう頑張りま~す

むくみとハイビスカス
2008年10月22日
 「足がむくんで、痛くって~
「足がむくんで、痛くって~ 」
」脚のアロマトリートメントを
受けに来られたお客様。
立ちっぱなしのお仕事のようです。
トリートメントの途中から、「痛みがなくなった~。気持ちいい~。」と歓声でした

疲れも溜まり、リンパの流れも滞っているんでしょうね。
サロンでのアロマトリートメントは、頑張っているご自分へのご褒美です。
癒しのひとときでリフレッシュされてください。
では、ご自宅でできるセルフケアは・・・?
そこで “ハイビスカス”

ハイビスカスとローズヒップのブレンドティーがおすすめです。
ハイビスカスにはカリウムが豊富に含まれていて、利尿作用があります。
また、クエン酸も多く含まれています。
クエン酸は、疲労物質の乳酸の排泄を促します。
健康な体内は弱アルカリ性に保たれているため、
乳酸が体内に溜まると、体が酸性に傾いて、倦怠感を与えます。
ビタミンCが豊富なローズヒップとハイビスカスのブレンドで、代謝アップ

太陽の光ををいっぱい浴びた真っ赤なハイビスカスとローズヒップ。
きれいな赤い色と酸味が疲れた体を癒してくれます。
むくみをとってお通じもOKですよ