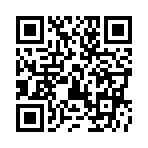スポンサーサイト
アロマセラピーのこと (精油)
2008年11月18日
アロマの歴史を辿っていくと、人と香りとの関係が深くて古いことに気づきます
現代のように生活が複雑でなく、シンプルだった頃は、“香り”はもっと生活に密着していたんでしょうね。
植物から抽出された「精油」を利用して心身を癒し元気づける「アロマセラピー」
アロマセラピーに欠かせない「精油」って何でしょう?
「精油」は「エッセンシャルオイル」といいますが、オイルという名に反して、油の成分の脂質類はほとんど含まれません。
でも、水には溶けず、油にはよく溶ける性質を持っているんです。
強いて言えばアルコールに近いもので、揮発性があり、ベタつく感触はありません。
「精油」の原料となるのは、植物の花や葉、種子や根、樹脂などいろいろです。
ハーブや柑橘類などの植物には、「油のう」と呼ばれる袋状の小さい粒があって、この粒の中に精油が入っています。
オレンジなどの皮の表面をよく見ると、透明感のある油のうが確認できますよ。
この「油のう」が花びら、樹皮、果皮、茎、葉の裏など、植物のいろんな部位にあって、そこから精油が採られます。
オレンジの皮をギュッと押さえると、“プチッ”と香りの強い液が出てきますよね
これがオレンジの精油です!
「植物のホルモン」とも呼ばれる精油。
根から水分や栄養を吸収し、たくさんの日光を浴びて育った植物は、自然が与えてくれた力を、自分が育つための力に変換させ、「油のう」にため込んでいるんです。
「精油」には、植物が大地や太陽から受け取ったパワーが凝縮されているんですね
どんな植物のどの部位から抽出されたかによって、
成分も私たちにもたらす影響も変わってきます。
「精油」の抽出法は、次回へ~!

現代のように生活が複雑でなく、シンプルだった頃は、“香り”はもっと生活に密着していたんでしょうね。
植物から抽出された「精油」を利用して心身を癒し元気づける「アロマセラピー」

アロマセラピーに欠かせない「精油」って何でしょう?
「精油」は「エッセンシャルオイル」といいますが、オイルという名に反して、油の成分の脂質類はほとんど含まれません。
でも、水には溶けず、油にはよく溶ける性質を持っているんです。
強いて言えばアルコールに近いもので、揮発性があり、ベタつく感触はありません。
「精油」の原料となるのは、植物の花や葉、種子や根、樹脂などいろいろです。
ハーブや柑橘類などの植物には、「油のう」と呼ばれる袋状の小さい粒があって、この粒の中に精油が入っています。
オレンジなどの皮の表面をよく見ると、透明感のある油のうが確認できますよ。
この「油のう」が花びら、樹皮、果皮、茎、葉の裏など、植物のいろんな部位にあって、そこから精油が採られます。
オレンジの皮をギュッと押さえると、“プチッ”と香りの強い液が出てきますよね

これがオレンジの精油です!
「植物のホルモン」とも呼ばれる精油。
根から水分や栄養を吸収し、たくさんの日光を浴びて育った植物は、自然が与えてくれた力を、自分が育つための力に変換させ、「油のう」にため込んでいるんです。
「精油」には、植物が大地や太陽から受け取ったパワーが凝縮されているんですね

どんな植物のどの部位から抽出されたかによって、
成分も私たちにもたらす影響も変わってきます。
「精油」の抽出法は、次回へ~!
久しぶりの“フェイシャルエステ”!!
2008年11月18日
月に1~2回お世話になっているTさんのエステサロン
もちろん、山都町(旧矢部町)です

今日は久しぶりの “自分へのご褒美”です
このところ、ちょっぴりハードな日が続いて・・・
お昼までの時間を自分のために使うことにしました
いつも明るくて前向きなTさん。
明るくて気持ちの良いサロン。
エステを受けながらの何気ない会話も、心をリラックスさせてくれます
施術が終わったところへ、Tさんのご親戚の方が3名来られて・・・・ティータイム

いつも和やかな空気が心地良い~~
人を癒してあげるためには、
自分自身を大切に、癒してあげないと!!
今日は、しっかり自分癒しができましたよ
充電完了~~

もちろん、山都町(旧矢部町)です


今日は久しぶりの “自分へのご褒美”です

このところ、ちょっぴりハードな日が続いて・・・

お昼までの時間を自分のために使うことにしました

いつも明るくて前向きなTさん。
明るくて気持ちの良いサロン。
エステを受けながらの何気ない会話も、心をリラックスさせてくれます

施術が終わったところへ、Tさんのご親戚の方が3名来られて・・・・ティータイム


いつも和やかな空気が心地良い~~

人を癒してあげるためには、
自分自身を大切に、癒してあげないと!!
今日は、しっかり自分癒しができましたよ

充電完了~~

アロマセラピーのこと (歴史①)
2008年11月18日
「アロマセラピー」ってなんでしょう?
アロマとは“芳香”(香りを嗅ぐこと)、
セラピーとは“治療法”という意味。
植物の中には香りを持っているものがあります。
その中の香りの成分を取り出して、私たちの身体の中に取り入れることでよい作用をもたらすこと、
それが、 「アロマセラピー」です。
「アロマセラピー」という言葉を生み出したのは、
フランスの科学者 ルネ・モーリス・ガットフォセ
1920年代になってからのことです。
実験中に片手に火傷を負い、とっさに近くにあったラベンダーの精油に手を浸けたところ、火傷は跡形も残らず驚くような早さで治ったというエピソードが残っています。
これを機に精油についての研究に取り組み、
「アロマセラピー(芳香療法)」という言葉が生まれました。
でも、 “香り”の歴史は遙か昔にさかのぼります。
古代エジプトでは紀元前3000年頃から、植物の浸出液を薬や化粧品、芳香剤として利用していたようです。
ミイラを作る際には、現在私たちがアロマセラピーで使用する“シダーウッド”や“ミルラ(没薬)”などの殺菌力の高い植物が防腐剤として使われていました。
ミイラの語源は、この「ミルラ」だと言われています。
古代ギリシャの「医学の父」ヒポクラテスは、
「健康は、芳香風呂に入り、香油マッサージを毎日行うことである。」と・・・!
芳香原料を伝染病の予防として焚くことを試みているようです。
古代ローマは、バラが生活にとても密着していた文明です。
ネロ皇帝は香り好きで、豪華なバラの花の宴会が開かれていたとか・・!
11世紀になって、植物から精油を作り出す蒸留法が開発されるとペストやコレラなどの感染症をはじめとする医療への応用も始まりました。
アロマの歴史辿るとまだまだたくさんのエピソードがあります。
数千年も前から植物に含まれる成分を、病気の予防や治療、生活そのものに利用してきたことに気づかされます。
日本でも、ゆず湯や菖蒲湯など、植物の芳香成分を利用する習慣がありますね!
アロマとは“芳香”(香りを嗅ぐこと)、
セラピーとは“治療法”という意味。
植物の中には香りを持っているものがあります。
その中の香りの成分を取り出して、私たちの身体の中に取り入れることでよい作用をもたらすこと、
それが、 「アロマセラピー」です。
「アロマセラピー」という言葉を生み出したのは、
フランスの科学者 ルネ・モーリス・ガットフォセ
1920年代になってからのことです。
実験中に片手に火傷を負い、とっさに近くにあったラベンダーの精油に手を浸けたところ、火傷は跡形も残らず驚くような早さで治ったというエピソードが残っています。
これを機に精油についての研究に取り組み、
「アロマセラピー(芳香療法)」という言葉が生まれました。
でも、 “香り”の歴史は遙か昔にさかのぼります。
古代エジプトでは紀元前3000年頃から、植物の浸出液を薬や化粧品、芳香剤として利用していたようです。
ミイラを作る際には、現在私たちがアロマセラピーで使用する“シダーウッド”や“ミルラ(没薬)”などの殺菌力の高い植物が防腐剤として使われていました。
ミイラの語源は、この「ミルラ」だと言われています。
古代ギリシャの「医学の父」ヒポクラテスは、
「健康は、芳香風呂に入り、香油マッサージを毎日行うことである。」と・・・!
芳香原料を伝染病の予防として焚くことを試みているようです。
古代ローマは、バラが生活にとても密着していた文明です。
ネロ皇帝は香り好きで、豪華なバラの花の宴会が開かれていたとか・・!
11世紀になって、植物から精油を作り出す蒸留法が開発されるとペストやコレラなどの感染症をはじめとする医療への応用も始まりました。
アロマの歴史辿るとまだまだたくさんのエピソードがあります。
数千年も前から植物に含まれる成分を、病気の予防や治療、生活そのものに利用してきたことに気づかされます。
日本でも、ゆず湯や菖蒲湯など、植物の芳香成分を利用する習慣がありますね!